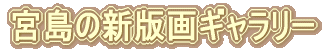
| 新版画とは 江戸時代末期に全盛を誇った伝統的浮世絵版画は、明治初期には日本人は浮世絵に見向きもしなくなり、二束三文で売られていた。木版画としての浮世絵の価値を見出したのは、外国人であった。いい浮世絵は外国人が買い占め、日本国内から消えたのである。版画の枚数が減るにつれ、元の版木から明治時代になっても後摺りされていた。版木が擦り切れると、複製版も作られるようになった。渡邊庄三郎は大正初期に複製版画を手がけるうちに浮世絵の妙味を深く理解し、大衆芸術としての版画を如何に復興すべきか研究した。新しい版画の製作過程は、これまでの浮世絵版画製作の良さを生かし、絵師、彫師、摺師による伝統的な分業体制のもとに行われた。そこでは、絵師の印象を表現できるまで摺師と何度も打ち合わせをし色に工夫を凝らし、場合によっては版木にも工夫を凝らした。さらに版元渡邊の助言を加えられ、最終産物として誕生した版画は、より芸術性の高い木版画となった。絵師のセンスが反映され、版画でしか表現できないグラディエーション(ぼかし)、木目の妙などを含めて肉筆画以上の味わいが生まれ、海外でも高い評価を得た。これらの作品は今日、「新版画」と呼ばれている。 このページでは、大正期以降の多色刷り木版画を、広義の「新版画」として、まとめて展示する。 |